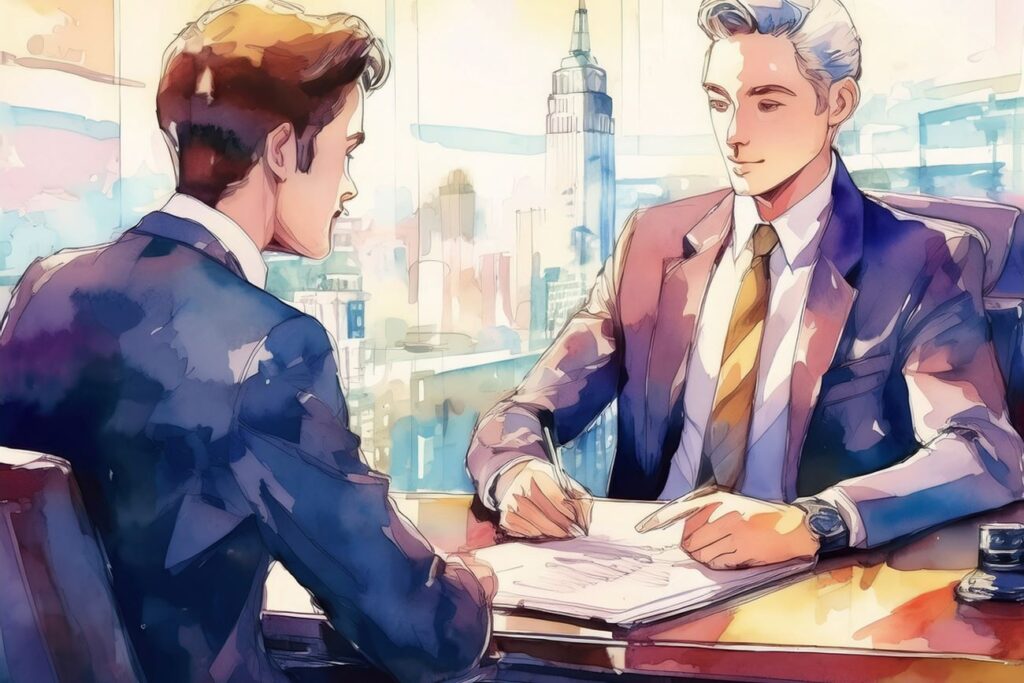
弁護士や公認会計士と気後れせずに会話している社長。
社長が会社に出入りしている弁護士や公認会計士、
そして税理士や社会保険労務士と対等に会話出来ているのはなぜ?。
そのような疑問を私は持ったことがあります。
その理由は、社長のその役割がスペシャリストではなくジェネラリストだからです。
よく考えいたら、そんな答えにたどり着きました。
会社は社長以下経営陣を各分野の専門家が支えてる仕組みになっている。
もう少し詳しく説明すると、
新しい分野に会社の成果領域を拡大しようと考えた場合に必要なことは、
市場規模、競合、将来性(成長性)、必要な資金と人材、その分野に関係する法律、経営体制、
資金、会社のポジションの変化。
思うだけでもこれだけのことが思い浮かびます。
それなの項目別に検討して最終的には経営計画を策定し、数字に落とし込みます。
数字の落とし込むというのは、中期計画のアクションプランと、
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)に落とし込みます。
本気で計画するから問題点や具体策の洗い出しが可能になる
そこで洗い出された問題点を解決するために専門家と相談する必要性が生まれてきます。
社長が弁護士や会計士、税理士と一歩も引けを取らずに渡り合えるのはジェネラリストだからです。
つまり、社長が経営計画の手綱を握っているからこそ、
弁護士や、会計士、税理士とともに、より専門的に問題点の解決の方向性を考えます。
社長に経営構想があるからこそ専門家に指示も出せる
社長に構想があるからこそ専門家に指示も出せるし、相談も出来ます。
一方の専門家も自分の役割がはっきりとイメージできることで、
良い仕事をしやすくなります。
弁護士や公認会計士、そして税理士や社会保険労務士の人たちは、
会社の顧問であれば日常的に会社に出入りして日常的な会話の中に、
会社な中計計画に従って進んでいくなかで有益なサジェスチョンがあります。
また、それは経営計画の共有がその根底にあります。


